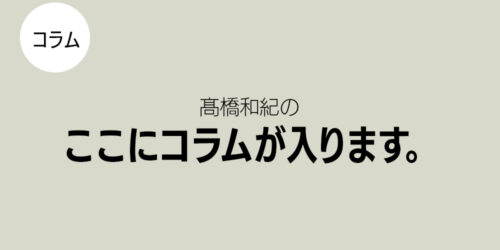ここにコラムが入ります。vol.3
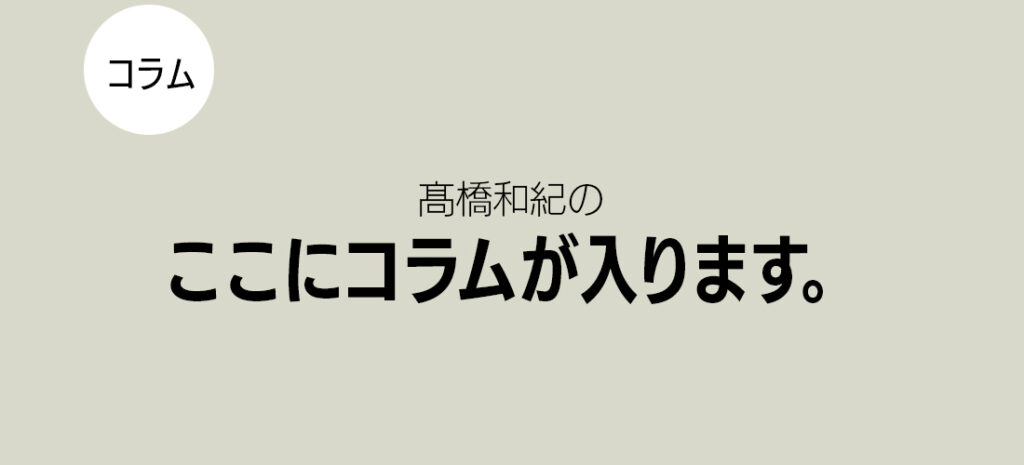
ご無沙汰しております。
スカイハイプロダクション髙橋でございます。
今日は2025年8月17日(日)、世間はお盆休みの最終日。
最後のコラムが2月だったので、6ヶ月ぶりの更新です…。
「文章を書く習慣をつけるぜ!」なんて言っておきながら、この体たらくぶりです。
無理せずに、「気が向いた時に更新する。」に力強く変更します。
今回は、継続することが苦手な私にしては珍しく長年継続している “写真” について書いてみたいと思います。
『海と山と街と』のSNSアカウントでも写真を投稿しているので、興味のある方もいるかもしれません。
はじめての
一眼レフカメラ
初めて一眼レフカメラを購入したのが18歳でした。
当時、学生でしたが、CGの仕事をフリーランスとして請け負っていて、その仕事のギャラ(人生初のギャラ!)が出たので、渋谷センター街の『カメラのさくらや』で Canon EOS 55(レンズキット)を購入しました。
今年48歳になるので、30年撮っていることになりますね。
(EOS 55 は今でも撮影できます。)
初めは、“撮る“という行為が面白くて、何も考えずに撮りまくっていました。
フィルム代や現像代も当時は安かったなぁ…。
考えてみると、つい最近までそうだったかもしれません。
スマホ
デジカメ
フィルムカメラ
現在はほとんどの人がスマートフォンを持っているので、搭載されているカメラで日常的に写真を撮っていますよね。“映え”というワードも定着 , X や Instagram , Facebook に投稿して楽しんでいる方も多いと思います。
私もiPhoneで写真を撮ることがありますが、メモ的なものしか撮りませんし、それ以外は撮る気になれません。
所詮はスマートフォンのレンズサイズとセンサーサイズなので、意図する写真が撮れないからです。
現在私が仕事”以外”で写真を撮るときに使っているカメラは、CONTAX RTSⅡで、レンズが Carl Zeiss 。デジタルではなく、フィルムカメラです。
CONTAX RTSⅡは、RTS Ⅰのポルシェデザインを踏襲したデザインに一目惚れ。
フェザータッチのレリーズボタンも堪りません。
Carl Zeiss は、言うまでもなく描写力が理由です。
あくまでフィルム時代の描写力ですが、電線などの線をとても綺麗に描写してくれます。
なぜ
フィルムなのか?
私は視力が弱いので、裸眼だと概ね全てがぼんやりします。
その見え方とCONTAX RTSⅡとCarl Zeissで撮ったフィルムの解像感がちょうどよいのです。シャープな部分と描写が弱い部分のバランスが、私の裸眼とフィットしているのです。
”気怠さを表現したい”という点からも、フィルムとオールドレンズの”写りすぎない”塩梅は、私に取ってはベストです。
仕事で使用している Canon R5 の画像(幅 9000px 程度)だと、私の視力以上の見え方になり、見て感じた印象と、高画質画像では違和感を覚えてしまうのです。
しかし、ポートレイト撮影は R5 で撮ります。
やはり人間の顔は高解像度で見たいので。
自分は
何を撮っているのか?
という最も核心的な課題が明確ではありませんでしたが、昨年、回答が出ました。
日常的に SNS に写真を投稿していたことが縁で、天津小湊にある『ギャラリー紫と緑』さんから、企画展のお誘いを受け、参加しました。
全てにおいてではありませんが、展示にはステートメント(写真の説明文)が必要になります。
私も初めてステートメントを書くことになり、自分の写真と向き合いました。
普段は朧げながら思考していましたが、文章にするとなるとなかなか厄介です。
何度も書き直しをし、人に読んでもらい、どうにか納得できるものが出来上がりました。
そのステートメントがこちら
展示時のステートメント全文
どこにでもある、
ここにしかない風景*
私は寝るときに、しばしばiPadを使ってグーグルマップを開く。
出鱈目に行ったことのない土地(大抵は辺鄙な土地)を
クローズアップし、ストリートビューに切り替える。
なんてことのない道が現れる。
知らない土地に、知らない人たちが住んでいる。
小さな家庭菜園を世話する誰か。
犬を散歩する老人。
自転車を漕ぐヘルメットをかぶった女子中学生。
ブロック塀に描かれた、誰も見ないようなグラフィティーアート。
Windowsマシンにプリセットインストールされたフォントの看板。
不釣り合いな高級セダンが停まっている空き地。
無名の川で釣りをしている少年。
彼らは私と同じように、日々を営んでいる。
知らない土地で、知らない人が、見慣れたような風景の中で…。
とても当たり前のことだけど、それが不思議に感じる。
その不思議さは、今のところ写真で表現するのが最も適していると
考えている。
この”写真を撮る動機”の核心を認識してから、写真へのスタンスがとてもクリアになりました。
巷間云われるスナップショットのスタンスとして「グッときたものを撮る」も理解できますが、かなり抽象的で納得感はありません。
それに比べて「ここで生活している僕が見ている風景」というコンセプトは明確です。私の視点ですからね。迷いがなくなったと言っても過言ではありません。
ただ、誤解されたくない要素の一つが、
“ノスタルジーを撮りたいわけじゃない”
です。
私の写真を構成する要素にノスタルジーがあることは自覚していますが、「懐かしい風景を撮りたい」ではないのです。
写真にイオンモールが写っていても、丸亀製麺が写っていても、そこにはノスタルジーを感じます。おそらく私の中で、“ノスタルジー=懐かしい”ではないのでしょうね。
例えば、廃墟や使われなくなった自販機などは、いわゆる“死んだもの”です。
私の写真は、“生きているもの”を写しています。死んだものが写っていても、それは生きている現在に内包された死んだものです。観念的でわかりづらい説明になってしまいますが、その通りなのです。
これから
撮影行為がクリアになってからは、“50年後に写真を見た人へのメッセージ”という要素も大事に感じています。
写真の恒久的な機能として、アーカイブ性があります。
“この風景をこのように撮っていた人がいた”は、後世にとって価値のあることだと認識しています。
私が50年前の名もない写真に共感を覚えるように、50年後の誰かが、私の写真に共感してくれたら何よりです。
これからも私は、その土地にいたであろう私が見ていた風景を撮り続けていくでしょう。
この写真は、Canon EOS 55 を買った日に撮った1枚。


『海と山と街と』編集長
(株)スカイハイプロダクション代表取締役 兼グラフィックデザイナー